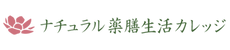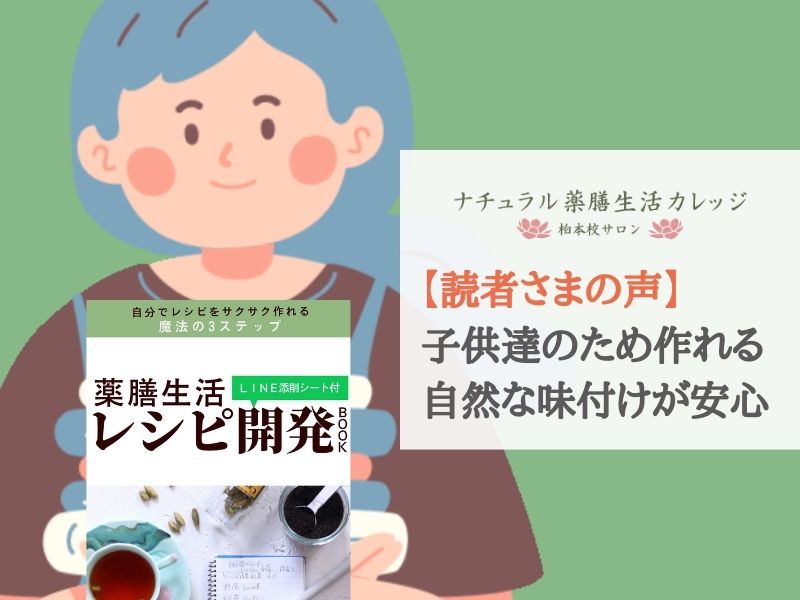2022年5月30日♊双子座新月に出版した電子書籍『薬膳生活レシピ開発BOOK Vol.5 梅雨 季節薬膳』に寄せられた「読者さまの声」。
とても嬉しく拝読させて頂きました。
薬膳テーマにはさまざまなカテゴリーがあります。
今日頂いた読者さまの声でわたくしの胸に一番響いたのは「母の愛」が伝わってくるコメント。

なぜなら今回共著者として名を連ねてくださった4人の皆さんも、みんなお母さんだったからです。
そこで今回は、「【読者さまの声】子供達にも安心して自然な味付けの薬膳を食べさせられそう」のお話しです。 余談ですが、自分はお腹を痛めて血のつながった子供を産む夢は叶いませんでした。 でもその代りに産もうと決めて2008年に開いた薬膳教室、「蓮蓉茶樓子(れんようちゃろうこ)」ちゃんは、薬膳スクール「ナチュラル薬膳生活カレッジ柏本校サロン」に成長を遂げました。 以下の写真は2ヶ月前、開校してから14年ぶりの外壁修繕の際に「蓮蓉茶樓」の看板の文字を金色に塗り直してもらって、嬉しかったときに仲良くしている業者さんに撮ってもらいました。
目次
電子書籍『薬膳生活レシピ開発BOOK』季節薬膳シリーズとは
『薬膳生活レシピ開発BOOK 季節薬膳シリーズ』は、昨年2021年8月8日♌獅子座新月「開校13周年記念日」に照準を合わせ、会員である修了生さん達と一緒に「夏版」から作り始めた「五行の季節薬膳の電子書籍出版プロジェクト」の結晶です。 薬膳は料理ではなく、中医学に基づく食事療法であることをやさしく社会普及するのが目的で出版しました。 だから、難しい中医学の専門用語はなるべく使わずに、誰でもカンタンに季節の不調を予防ケアする薬膳レシピを開発出来るように工夫されています。 コロナ禍に入ってから電子書籍の出版の方法を学び、寄稿者の皆さんと共同作業で原稿をまとめ上げ、薬膳ライフコーチが責任を持って監修。 編集と構成も全て手作りでこなしました。 そして先月末、2021年5月30日♊双子座新月に五行の季節最後の5冊目「梅雨版」の出版を実現したばかり。 今回ご紹介する読者様の声は、この梅雨版についてのKindle版アマゾンブックレビューです。 薬膳のみなもと中国の古代哲学の考え方では、季節を含めこの世の全ては5つのカテゴリーから成り立っています。 こうした古代人の宇宙観・自然観に基づいて、春・梅雨・夏・秋・冬の5つの季節特有の不調に対する予防とケアの薬膳の開発方法を「超入門」で分かりやすく書き下ろしました。 各巻には、それぞれの季節に起こりやすい代表的な不調を例として4分類ずつ挙げています。 まさに一昨日梅雨入りしたばかりなので梅雨版を例に挙げると、 ・ムシムシ感 ・梅雨寒の冷え性 ・胃腸のトラブル ・水太り重だるさ この季節に特有の不調を主なものとしてこれら4つに分類しました。 そして、それぞれの分類に対して薬膳レシピ開発のコツと、誰でもカンタンに作れる家庭薬膳のレシピ例を5つずつ収載。 1巻につき、20例の季節薬膳のレシピが収載されているので、全5巻で五行の季節薬膳100レシピ例が出揃っています。 季節の不調を改善するのに薬を飲む前に、まずは食事で予防とケアを出来ることを一人でも多くの人たちに知って欲しい。 そんな思いでしたためたので、カレッジの「ナチュラル薬膳生活専門家養成コース」とは異なり、専門用語は一切排除。 その想いを受け止めてくれたお子様への愛情たっぷりな読者さまから、五行最後の梅雨版に嬉しいご感想を頂いたので、次にご紹介します。お母さんが開発する薬膳はほとんどが子供薬膳に応用が利く
『薬膳生活レシピ開発BOOK Vol.5 梅雨 季節薬膳』にレビューを寄せて下さったふるかわ様によると、食材が普段つかう材料ばかりだったので、「これならできそう!」と思ったのだとか。 当スクールでは、出来るだけ化学的に合成した調味料を使わないで薬膳レシピを開発しているのが伝わっているがとても嬉しかったです。 こうした体にやさしい調味を心がけている点を、「自然な味付けなども魅力的」とご評価くださいました。 そして一番嬉しかったのが、「子供たちにも安心して食べさせられそうです。」とおっしゃってくださったのですね。 日頃から、子供さん達の健やかな成長によい食事を摂らせてあげたいという「母の愛」をひしひしと感じるコメントでした。 冒頭でお話ししたとおり、この梅雨版の共著者も実は全員がママなのです。
もちろん、この季節薬膳のプロジェクトのご参加にあたっては、主旨が季節テーマなのは十分理解してくださっていました。
だから、梅雨の不調の予防とケアにそれぞれの分類でとても役立つレシピではあるのですが・・・
どの共著者の皆さんのレシピも、2歳から12歳くらいまでのお子さん達がご家庭で大人と一緒に食べられる消化によいお料理に仕上がっていました。
だからお母さんの薬膳の専門家が開発するレシピは、そのほとんどが子供薬膳に応用も利くのです。
わたくしが開発したレシピもやさしい味で消化の良いものがほとんどですが、中には梅雨冷え対策に体を温めるために敢えてスパイシーな大人向きの薬膳も含めました。
ここが薬膳ライフコーチと共著者が提案している梅雨の季節薬膳との大きな違いです。
だからふるかわさんには是非、薬剤師マヤンレメディストの絵理さんが2歳のお子さんに実際に作ってあげている「枝豆と玉ねぎの食べるスープ」などを参考に、ご自身のオリジナル薬膳を開発してみて欲しいと思っています。
ちなみにこちらのレシピも、体を温め水毒を体の外にデトックスする「梅雨寒の冷え性の予防とケア」に役立つ処方になっています。
「薬膳との距離が少し縮まった気がします。」ともコメントしてくださったので、これからは身近な食材を応用して気軽に子供薬膳も作ったりし始められることでしょう。
未来を創る子供さん達を薬膳レシピ開発で健やかに丈夫に幸せに、育てて頂きたいと願っています。
冒頭でお話ししたとおり、この梅雨版の共著者も実は全員がママなのです。
もちろん、この季節薬膳のプロジェクトのご参加にあたっては、主旨が季節テーマなのは十分理解してくださっていました。
だから、梅雨の不調の予防とケアにそれぞれの分類でとても役立つレシピではあるのですが・・・
どの共著者の皆さんのレシピも、2歳から12歳くらいまでのお子さん達がご家庭で大人と一緒に食べられる消化によいお料理に仕上がっていました。
だからお母さんの薬膳の専門家が開発するレシピは、そのほとんどが子供薬膳に応用も利くのです。
わたくしが開発したレシピもやさしい味で消化の良いものがほとんどですが、中には梅雨冷え対策に体を温めるために敢えてスパイシーな大人向きの薬膳も含めました。
ここが薬膳ライフコーチと共著者が提案している梅雨の季節薬膳との大きな違いです。
だからふるかわさんには是非、薬剤師マヤンレメディストの絵理さんが2歳のお子さんに実際に作ってあげている「枝豆と玉ねぎの食べるスープ」などを参考に、ご自身のオリジナル薬膳を開発してみて欲しいと思っています。
ちなみにこちらのレシピも、体を温め水毒を体の外にデトックスする「梅雨寒の冷え性の予防とケア」に役立つ処方になっています。
「薬膳との距離が少し縮まった気がします。」ともコメントしてくださったので、これからは身近な食材を応用して気軽に子供薬膳も作ったりし始められることでしょう。
未来を創る子供さん達を薬膳レシピ開発で健やかに丈夫に幸せに、育てて頂きたいと願っています。
梅雨版の表紙の「カルダモン紅茶」薬膳レシピ開発理論
今日配信したライブでは『薬膳生活レシピ開発BOOK Vol.5 梅雨 季節薬膳』の表紙に載っている「カルダモン紅茶」についても、どのような薬膳の理論で組み立てたのか軽く触れました。 ですので、こちらも簡単にご紹介させて頂きます。 この薬膳茶は先に説明した梅雨の典型的な4つの不調のうち、梅雨寒の冷え性の予防とケアのレシピ例として開発。 薬膳素材でもある身近な茶材、紅茶には体を温めてむくみを利尿で改善する働きがあります。 ですから、温かい紅茶を飲むだけでも梅雨の冷えを改善するにはとても役立つのです。 この作用にプラスしてナチュラル薬膳生活では、スパイス系のさまざまな薬膳素材を組み合わせて相乗効果を得ることがあります。 カルダモンのホールをカットしてフレッシュな種をティーポットで一緒に淹れるだけで、体の中から湿気を追い出す働きを簡単に加えられるのですね。 カルダモン紅茶については、過日に以下のブログにも書いたので、詳細はそちらでお読み頂けます。 https://natural-yakuzen.com/yakuzen-lifestyle/cardamom-tea20220420/まとめ【読者さまの声】子供達にも安心して自然な味付けの薬膳を食べさせられそう
今回は子供薬膳にも応用が利く消化によいレシピ例が満載の『薬膳生活レシピ開発BOOK Vol.5 梅雨 季節薬膳』に寄せて頂いた読者様の声にフォーカス。 読者さまがこの本のレシピ例を見て、ご自身の子供さん達にも安心して食べさせてあげられそうと言ってくれたのが一番嬉しかった理由を紹介しました。 それは、共著者の皆さんが子育て中のママさん達で、読者さまと同じ思い、母の愛で家庭料理を作っていらっしゃる姿が重なったから。 今回頂いた読者さまの声はライブ配信でもご紹介させて頂いたのですが、その中で梅雨版の表紙の薬膳茶、カルダモン紅茶についても紹介しました。 梅雨寒の冷え性の緩和に手軽に作れる薬膳茶なので、こちらのブログをご覧になった薬膳の専門家を目指す皆さまにもお試しいただけたら幸いです。 須崎桂子けいてぃー♪ 参考文献: 須崎桂子・中山絵理・沼田香余・川原明名・浅野美穂著 『薬膳生活レシピ開発BOOK Vol.5 梅雨 季節薬膳』