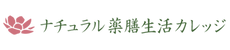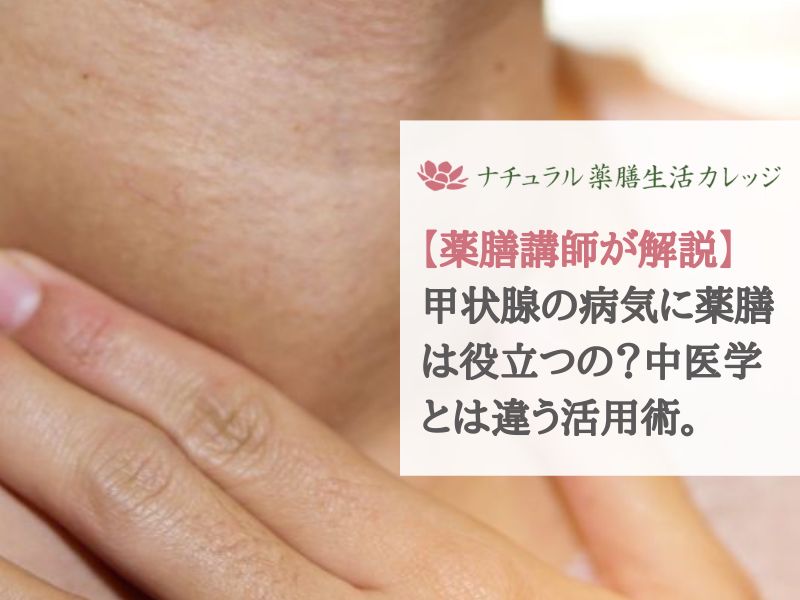こんにちは。薬膳講師歴15年の須崎桂子です。

甲状腺の病気が気になるという声。薬膳講師を長く務めていると、耳にすることが。。。
小学生の頃に母がバセドウ病で相当だるそうだったので、他人事とは思えない病気です。
薬膳は、東洋医学に属する中医学の食事療法。
現代医学とは違う東洋医学の強みを活かすと、甲状腺の病気に薬膳は役立ちます。
よって東洋医学と現代医学の違いを踏まえ、バセドウ病と橋本病に対する薬膳の活用術を紹介。
この記事では、甲状腺ホルモンの病気は、分泌量を調節する甲状腺機能異常(機能低下「橋本病」、機能亢進「バセドウ病」)が対象。短く、「甲状腺の病気」といいます。
目次
治療法が根本的に違う「東洋医学」と「現代医学」
東洋医学と現代医学はそもそも人体観が次のように異なります。
人体観が正反対なので、病気に対する認識と治療法が根本的に違うのは当然のこと。
東洋医学の病気に対する認識と治療法
東洋医学では病気の原因を、心・体・生活環境、全体のバランスの崩れと捉えます。
病気の治療にあたっては、症状を訴える体の部分だけを診ることはしません。
・心に関わる精神状態はどうか
・体の他の部分にも不調はないか
・家庭や職場の環境はどうか
・季節変化など天候の影響はどうか
最初にさまざまな角度から病気の原因を究明して、クライアントから心と体の状態をトータルに把握。
病気は心や体の一部分の失調が、全体のどこかに悪影響を及ぼして起こる異常事態と捉えるからです。
生活環境や自然界の天候変化も考慮して、先人の経験則も参照しながら心と体の状態を分析。
そのうえで、本来の健やかなバランスを取り戻す治療法を採用します。
病気の種類によりますが、失調している部分だけを直接治療することはほとんどないので、即効性に欠けるのがデメリット。
その代わり、じっくり体調を整えて体質を改善。時間をかけて慢性病を治すのが得意。長い目で見ると年齢に応じて、質の良い健康状態を保つことができるのがメリットです。
東洋医学の治療法には、漢方クリニックであれば、日本漢方。鍼灸院であれば、ツボへの鍼灸刺激。中医学の食事療法であれば、薬膳などがあります。

現代医学の病気に対する認識と治療法
現代医学では病気の原因を、症状を起こしている臓腑器官などの部分的な生理機能の失調と捉えます。
そして病気を治療するために、症状を起こしている部分がどんな異常を起こしているか精密に検査します。
・失調している臓器など体の部分を特定
・失調が正常値と比べてどの程度異常か把握
症状を起こしている体の部分を特定したら、異常を数値化または視覚化して科学的に分析。
どこがどう異常なのか究明したら、病気の臓腑器官を直接治療する方法を採用します。
生命に関わる急性病であれば、すぐに症状を把握して速やかな外科手術に至ることもあるでしょう。
慢性病には症状を緩和したり、臓腑器官の機能の異常値を正常に戻したりする、薬物療法が一般的。
感染症による異常な高熱や、緊急な外科手術が必要な脳梗塞などは、現代医学の力を要する病気です。
まず命を救うのが先決の病気には、即座に手を打てることが多いのがメリットといえるでしょう。
但し病気の種類によりますが、薬物療法による副作用、生涯にわたる服薬、後遺症のリハビリなど、たとえ治療を終えても生活の質に関わる課題が残りうるデメリットもゼロではありません。

現代医学の病院では、精神病は心療内科、心臓病は循環器科、耳や鼻の病気は耳鼻科、皮膚病は皮膚科・・・のように、病気の種類によって治療を担う専門医が細かく分かれています。
その理由は、人体は部分の組み合わせで構成され、機能していると考えるから。
一方、東洋医学の漢方クリニックでは、病名で専門医が分かれていることはほとんどありません。
人体は心も体も含め、全体がひとつとして機能していると考えるからです。
甲状腺の病気に対する中医学の捉え方と薬膳実践
薬膳は、東洋医学の一種である中医学理論で組み立てる食事療法。
中医学の視点から甲状腺の病気の原因を捉えて、薬膳の実践に活かします。
病気の原因は「陰陽バランス」の崩れ
中医学理論によれば病気の原因は、全体のどこか一部に生じた陰陽バランスの崩れ。
甲状腺の病気に対する薬膳の捉え方も、心・体・生活環境、どこかに陰陽バランスの乱れが生じたから、ホルモン分泌の機能が異常になったと見做します。
陰陽バランスは、中国古代哲学の陰陽学説の世界観。人体を含む森羅万象は、静的かつ物質的な「陰」と、動的かつ機能的な「陽」、正反対の性質を持つ陰陽二極から成り立っている状態と考える。
例)精神状態であれば、鎮静は「陰」、興奮は「陽」。甲状腺ホルモンの内分泌系であれば、分泌抑制は「陰」、分泌促進は「陽」。人間の生物学的な性別であれば、女は「陰」、男は「陽」。
例えば、劣悪な住環境や職場でのパワハラなど環境による外的ストレスで交感神経が高ぶり、陽の興奮状態が長引いたとしましょう。
心を陰の鎮静状態に戻せないと、自律神経系の陰陽バランスが中庸からかけ離れて長い間緊張状態が続きます。
過剰な陽の偏り状態が、知らないうちに内分泌系の甲状腺に影響し続けたら、一体どうなるでしょう?
心と体は繋がっているので、ストレス状態が間接的に内分泌異常をおこしても不思議ではありません。
つまり、分泌過剰のバセドウ病、または、分泌低下の橋本病を引き起こすかもしれないのです。
生理機能は複雑なので、ストレスと甲状腺の病気の因果関係を科学的に実証したくても難しいもの。
しかし東洋医学では長い臨床経験を経て、心と体と環境の陰陽バランスが健康を左右すると考えてきました。
昔から「病は気から」と言われる理由は、東洋医学にあるのです。
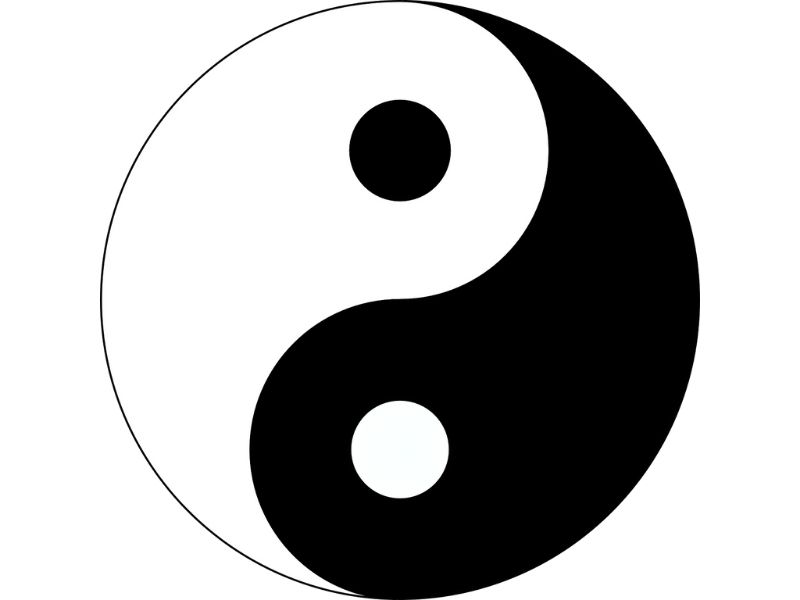
薬膳実践で症状を間接的に「緩和」
甲状腺の病気に対する薬膳実践は、バセドウ病や橋本病の症状を間接的な緩和するのに活用します。
東洋医学は直接、甲状腺ホルモン分泌の機能を直接的に抑制・促進する治療をしないから。
中医学理論では、分泌異常を起こしている「陰陽バランス」の原因を探求。
症状を緩和しながら全体を整えて、徐々に健康を取り戻す治療を行います。
薬膳は、この中医学の治療のひとつに用いる食事療法。
現代医学の治療にも併用でき、副作用による症状の緩和にも役立ちます。
薬膳実践の方法論には、さまざまな不調に対して薬膳素材をどう選んで調理すべきか、具体的な指針が示されているからです。
薬膳素材は中医学に基づく薬膳の視点から、不調の改善に対して特有の働きを持つ食材や生薬。主な働きに応じて体系的な分類があります。
例)橋本病でからだ冷えが生じたら、温める作用のある胡桃を使って薬膳を組み立てる。

バセドウ病と橋本病に対する薬膳の活用術
甲状腺ホルモンの病気に対して、薬膳は具体的にどう実践するのでしょう?
まず、ホルモン分泌過剰のバセドウ病と、反対に分泌低下の橋本病、それぞれ特有の症状を把握。
中医学理論を踏まえて、薬膳の食事療法を組み立てて食し、それぞれの不調を緩和します。
東洋医学は体の組織・器官・血液・生体エネルギーは、毎日の食事から作られ、心は体と繋がっていると捉えるから。
現代医学でバセドウ病や橋本病の治療を始めても、心や体の症状はなかなか改善しないかもしれません。
薬物療法や手術で副作用が出ている人がいるかもしれません。
薬膳は現代医学の治療中に併用して、不調を食事で緩和するのにもお役立ち。
病気の治療後も薬膳生活を続ければ、心身の陰陽バランスが整うので、再発防止も期待できます。
ではバセドウ病、次に橋本病の主な症状とレシピ例を交えて薬膳の活用術を紹介します。
バセドウ病の症状を緩和ケアする薬膳の活用術
陽の状態のように甲状腺ホルモンの分泌が亢進するバセドウ病。

次のような症状が見られるので、薬膳では陰の落ち着かせる方向に持って行きバランスを中庸に近づける食事療法を行います。
バセドウ病の主な症状
・食欲が亢進して食べるのに痩せる
・心臓がドキドキする
・脈が速くなる
・イライラする
・疲れやすい
・息切れする
・暑がる
・下痢する
・眼球が飛び出してくる
・首が腫れてくる
バセドウ病の症状に対応する薬膳の食材と調理法選びの基本は、
・エネルギーを補給する:動物性や植物性のたんぱく質、穀類、ビタミン・ミネラル豊富な野菜類
・亢進を鎮静させる:香りのよい柑橘類や香味野菜
・冷ます:みずみずしい野菜、果物、豆腐
・下痢を止める:緑茶、栗の渋皮煮、山芋、蓮の実
・呼吸器をいたわる:山芋、蓮根
・細胞の生成を助ける:ビタミンC豊富な野菜や果物、亜鉛を含む牡蠣や卵や種実類
補足ポイント:
・甲状腺ホルモンの材料のヨウ素を含む海藻類、特に含有量が多い昆布を控える
・魚類にもヨウ素が含まれていることが多いので摂り過ぎない
・亢進による消耗をひどくする刺激の強いスパイスや飲食物を控える
バセドウ病の症状を緩和する薬膳レシピ例「舞茸豆腐の鶏そぼろ葛あん」
バセドウ病の緩和ケアの考え方に則して、薬膳を組み立てるとどうなるでしょう?
具体例として、「舞茸豆腐の鶏そぼろ葛あん」をご紹介します。

作り方は、舞茸と鶏ひき肉と生姜を炒めて豆腐をプラス。水溶き本葛粉でとろみづけ。茹でグリーンピースか香味野菜をあしらって供します。
本葛粉の代わりに片栗粉でとろみをつけてもOK。本葛粉と片栗粉の薬膳的な違いを知りたい方は、こちらの記事をご参照ください。
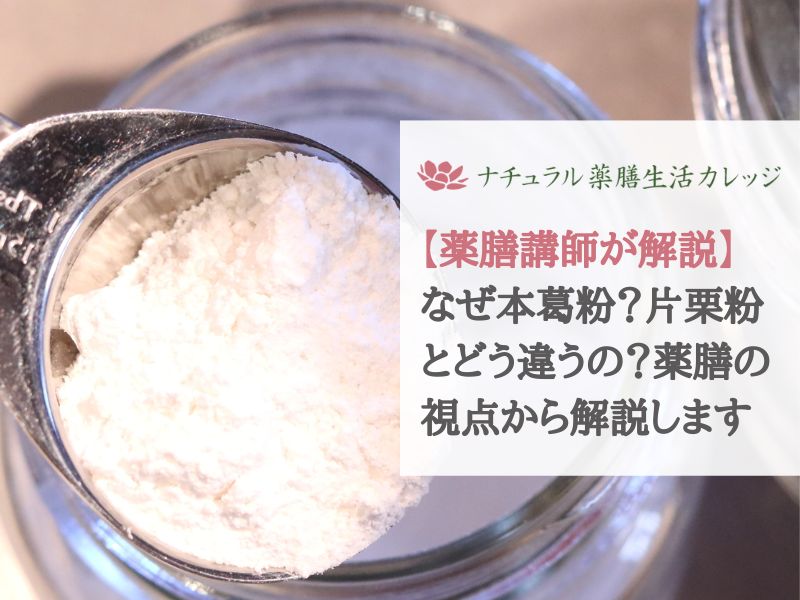
バセドウ病の症状を緩和ケアする薬膳の理由:
・口当たりが柔らかいあんかけ料理。消化がよく、温かい調理法
・舞茸とひき肉。亢進により消耗したエネルギーを補給する、植物性と動物性の薬膳素材
・生姜やえんどう豆や香味野菜の香り。イライラなど興奮による精神状態を、鎮静・調整
・豆腐や本葛粉。温める調理法を用い、緩やかに心と体を熱冷まし
橋本病の症状を緩和ケアする薬膳の活用術
陰の状態のように甲状腺ホルモンの分泌が低下する橋本病。

次のような症状が見られるので、薬膳では陽の気力アップの方向に持って行きバランスを中庸に近づける食事療法を行います。
橋本病の主な症状
・全身に倦怠感があって疲れやすい
・運動や精神活動が鈍くなる
・顔の目の周りやあごが浮腫む
・寒がる
・体重が増える
・便秘
・眉毛の外半分が抜ける
橋本病の症状に対応する薬膳の食材と調理法選びの基本は、
・エネルギーを補給する:動物性や植物性のたんぱく質、穀類、ビタミン・ミネラル豊富な野菜類
・心身をしゃきっとさせる:香りのよい柑橘類や香味野菜
・温める:葱や生姜など辛味で発散する野菜類
・老廃物を解毒する:食物繊維を摂れる芋類、野菜、果物
・細胞の生成を助ける:ビタミンC豊富な野菜や果物、亜鉛を含む牡蠣や卵や種実類
補足ポイント:
・適度にヨウ素を含む海藻類を摂る
・ヨウ素は過剰摂取すると、かえって甲状腺ホルモン分泌を低下させるので摂り過ぎない
・ゴイトロゲンという抗甲状腺物質を含むアブラナ科の野菜を摂り過ぎない
・消耗をひどくする刺激の強いスパイスや飲食物を控える
橋本病の症状を緩和する薬膳レシピ例「鱈とじゃが芋の生姜蒸しワカメ添え」
橋本病の緩和ケアの考え方に則して、薬膳を組み立てるとどうなるでしょう?
具体例として、「鱈とじゃが芋の生姜蒸しワカメ添え」をご紹介します。

作り方は、鱈とじゃが芋に生姜をのせて蒸し煮するだけ。ワカメと紫蘇を添えて召し上がれ。
橋本病の症状を緩和ケアする薬膳の理由:
・食材がしっとり柔らかくなる蒸しもの。消化がよく、温かい調理法
・鱈とじゃが芋。エネルギーを補給する、動物性と植物性の薬膳素材
・生姜や紫蘇の香り。心身をしゃっきりさせて、鈍化した運動や精神活動を程よく刺激
・食物繊維豊富なじゃが芋やワカメ。老廃物とともに腸管から、お通じ改善
・じゃが芋のビタミンC。細胞の生成や、エネルギー代謝を促進
・ヨウ素の含有量が少なめの海藻類ワカメ。程よくヨウ素を補給
まとめ
東洋医学に属する中医学の食事療法、薬膳が甲状腺の病気に役立つことを解説しました。
ここで対象としたのは、甲状腺ホルモンの分泌過剰のバセドウ病と分泌低下の橋本病。
甲状腺の病気には、一般的にまず直接治療を行う現代医学が使われます。
しかし間接的な東洋医学の治療も併用したい方のために、東洋医学と現代医学の長所と短所を比較。
東洋医学から生まれた中医学の食事療法、薬膳が甲状腺の病気を陰陽バランスの崩れと捉えることを説明しました。
東洋医学の間接的な手法を使う薬膳が、甲状腺の病気に対して行うのは、全体のバランスを整えて、症状を緩和すること。
バセドウ病と橋本病の緩和ケアに、中医学理論を用いて薬膳をどう実践するのか。症状に対して適切な薬膳素材や調理法を選ぶ基本姿勢と、レシピ例も具体的に紹介しました。
甲状腺の病気の治療に、東洋医学のひとつである中医学の食事療法、薬膳を役立てたい皆さんの参考になれば幸いです。
参考文献:
須崎桂子著『ナチュラル薬膳生活入門編』
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」
講談社『新版病気の地図帳』
成長科学協会 研究年報 No.34 2010『日本人成人のヨウ素摂取量と甲状腺機能との関連について』
厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」
伊藤病院 甲状腺を病む方々のために 「ヨウ素と甲状腺の関係」https://www.ito-hospital.jp/06_iodine/01_about_iodine.html