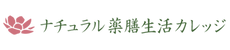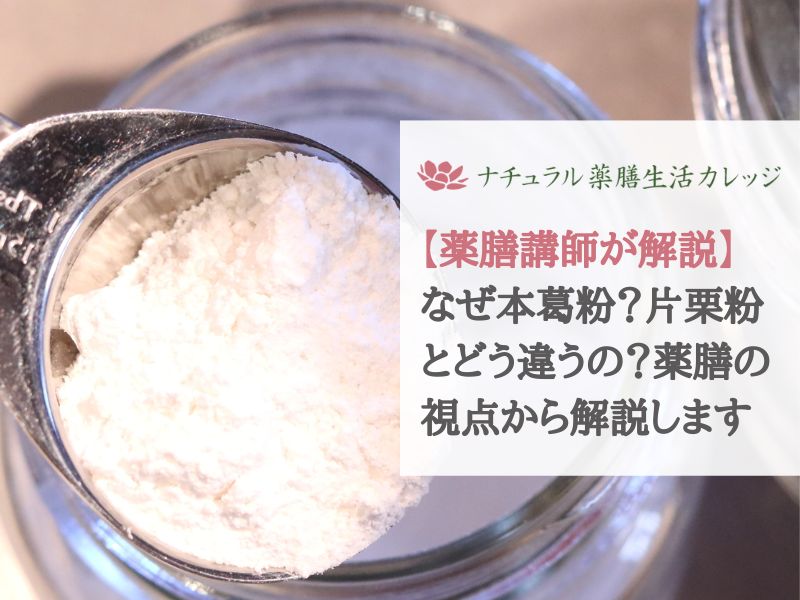こんにちは。薬膳講師歴15年の須崎桂子です。

薬膳のレシピを見ると最後のとろみ付けに、手軽な片栗粉でなく高価な本葛粉を使っているのに気づいたことはありませんか?
薬膳に興味を持つ皆さんの中には、「なぜ本葛粉なのだろう?」と思った方、いらっしゃるのではないでしょうか?
と言うのも二十年近く前、自分が最初に薬膳レシピの本を見たときにそう感じたからです。
同じ疑問でもやもやしながら、レシピどおり本葛粉で、または代わりに片栗粉で、薬膳にとろみを付けている皆さん。
今回は敢えて薬膳の視点から本葛粉と片栗粉の違いを解説します。
目次
中医薬膳学的な働きが違う「本葛粉」と「片栗粉」
本葛粉と片栗粉はさまざまな調理に使えますが、どちらもとろみ付けに便利。
水分の多い料理に加えて混ぜながら加熱すると、透明感のあるあんや、とろみスープが出来あがります。

おなじとろみ付けでも、薬膳で本葛粉と片栗粉を使い分ける理由。それはズバリ、薬膳素材として捉えると違う働きがあるからです。
薬膳素材とは、中医学に基づく薬膳の視点から、特有の働きを持つ食材や生薬のこと。主な働きに応じて体系的な分類があります。
片栗粉も本葛粉も、脳や体のエネルギー源となる炭水化物のでんぷんが主成分。よって現代栄養学と中医薬膳学、どちらの視点においても、生体エネルギー(気)を供給する加工食品です。
しかし薬膳の視点に基づくと、主要な働きが異なるので、薬膳素材としての分類は別々。
本葛粉と片栗粉の主な働きを、薬膳素材の分類に基づいて解説します。
体表の熱を除く薬膳素材「本葛粉」
中医薬膳学で本葛粉の働きを捉えるには、原材料の葛(クズ)の塊根から判断します。
本葛粉は精製された加工食品ですが、由来は生薬の葛根(カッコン)と同じ植物。
本葛粉は体表の熱を除く薬膳素材に分類されています。 体表の熱は感冒や発疹の初期症状の発熱のこと。
葛根は古来、カゼの初期症状に処方する葛根湯に配合されているので日本でも有名ですね。
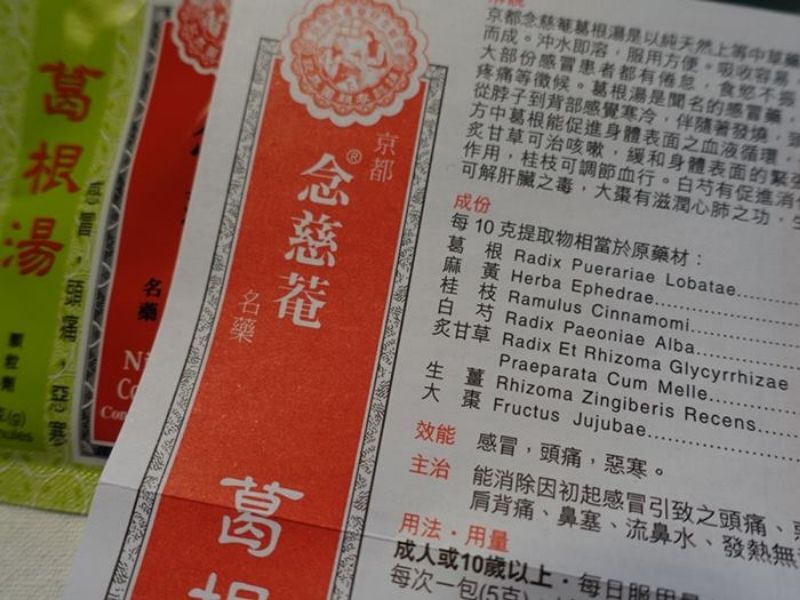
葛根はまだ症状が軽いうちに体表の熱を冷まし、熱によるのどの渇きを癒し、熱で奪われた体液を補給するため、漢方薬に配合されています。
葛根の使われ方を応用して、本葛粉は体の表面に生じた熱感の改善や、のどの渇きを癒す潤い補給を目的とした薬膳を組み立てる際に選びます。
感染症による初期の発熱ケア、のぼせによるホットフラッシュ改善、熱中症の予防などにも応用するとよいでしょう。
気を補給する薬膳素材「片栗粉」
中医薬膳学で片栗粉の働きを捉えるには、原材料のじゃが芋から判断します。
じゃが芋は気を補給する薬膳素材に分類されています。 気は生命活動を維持する生体エネルギーのこと。

中医薬膳学的に見ると体にエネルギーを補給するほか、消化吸収を担う臓器の働きを助けます。
だから疲労や病後や体質などの原因で虚弱なため、元気になりたい人の食事療法にお勧め。
消化吸収力が弱くて、食べても食べてもなかなか太れない体質や体調の人にも向いています。
不調がなくても、健康増進、お子さんの成長促進、緩やかなエイジングのため、薬膳を組み立てるのに使うのもよいでしょう。
とろみ薬膳「本葛粉」と「片栗粉」活用例
中医薬膳学の視点から本葛粉と片栗粉の違いを理解したら、中華あんかけ料理などを参考に、とろみ薬膳を組み立ててみるとよいですね。
体表の熱を冷ましたいのか、気を補給したいのか、目的に合わせてどちらかの薬膳素材を選ぶのがポイント。
どちらでもとろみを付ける調理法は食べやすいので、体内に入ってきた食材が消化吸収され、薬膳素材の働きがしっかり効いてきます。
ここでは活用例として、実際に薬膳ライフコーチと生徒さまが組み立てた本葛粉と片栗粉のとろみ薬膳を、それぞれ紹介します。
本葛粉のとろみ薬膳「葛あん仕立てのカニ玉にゅうめん」
薬膳ライフコーチが組み立てた「のぼせ」を改善する、本葛粉でとろみをつけた春の季節薬膳「葛あん仕立てのカニ玉にゅうめん」。

のぼせによる熱感を冷ます薬膳素材として、本葛粉のほかに小麦やカニを使っています。
なぜ、春はのぼせを予防する熱冷ましの薬膳なのか?
中医学では、春の陽気は草木を上へ上へぐんぐん成長させるのと同じく、人間の体内の気も頭のほうに上昇させ、ときに度を超すとのぼせを生じると考えるから。

人は気が昇り過ぎると、のぼせて熱っぽくなったり、イライラ怒ったりしがち。
とろみのある薬膳の柔らかな食感には、イラっとした気持ちを和らげる働きが期待できます。
そして春は、植物たちが地中の養分を吸って大きくなるのと同じく、人も体液をたくさん使って体内の潤いを消耗します。
潤い不足は熱感を助長して、さらに体の潤いを奪う悪循環につながりやすいもの。
「葛あん仕立てのカニ玉にゅうめん」の目的は、こうした春に起こりやすい熱感や潤い不足の改善です。
体液の一部である女性ホルモンの減少で起こる更年期障害のホットフラッシュや、夏の暑気あたりによる熱中症に対してもお役立てください。
ご参考に本葛粉をとろみ付けに使うには、予めミルで粉末状に砕いて瓶に入れて保存しておくと便利です。

本葛粉はお店で買うと、白いチョークを割ったようなブロック状の塊で袋に入っているからです。

本葛粉は粉末にしておくと水に溶かしやすいので、とろみを付ける薬膳の調理がスムーズになります。
片栗粉のとろみ薬膳「麻婆アスパラガス」
生徒さまが小学校に上がる前の小さな娘さん達のために、豆板醤を入れずに片栗粉でとろみをつけた子供薬膳《辛くない》「麻婆アスパラガス」。

気を補給する薬膳素材として、植物性の片栗粉のほかに、動物性の豚ひき肉がたっぷり使われています。
薬膳素材の気は、子供さん達の健やかな成長を促すエネルギー源にもなります。
とろみが嚥下(えんげ・食材をかんで飲み込むこと)を助けるので、子供だけでなくシニアにも食べやすい家庭薬膳。ぜひ参考にしてください。
まとめ
薬膳のとろみ付けによく使われる「本葛粉」が、一般的な「片栗粉」とどう違うのか、薬膳の視点から解説しました。
普通の料理にとろみをつけたいだけなら、どちらも現代栄養学的にはエネルギー源となる炭水化物が主成分なので、ほぼ同じ。どちらでも構いません。
中医学に基づく食事療法「薬膳」に使う場合は、本葛粉と片栗粉は働きが違うので、目的に応じて使い分けます。
葛の根が原材料の本葛粉は、春ののぼせ、更年期障害のホットフラッシュ、夏の熱中症といった症状を予防・緩和するのに役立ちます。
原材料がじゃが芋の片栗粉は、滋養を必要とする虚弱な人、育ち盛りの子供たち、緩やかなエイジングを目指すシニアの方などに向いています。
薬膳を組み立てる際は、食事療法の目的に応じて本葛粉と片栗粉を使い分けるとよいでしょう。
「薬膳実践コース」では、薬膳に現代の栄養学や生理学の知見も掛け合わせて、心と体の健康管理に役立つ暮らし方「ナチュラル薬膳生活」を教えています。
今回のお話が、自分で薬膳を組み立てられるようになりたい皆さんのお役に立てば幸いです。
参考文献:
須崎桂子著『ナチュラル薬膳生活入門編』
須崎桂子監修「葛あん仕立てのカニ玉にゅうめん」レシピ担当須崎桂子『薬膳生活レシピ開発BOOK Vol.4 春 季節薬膳』
須崎桂子監修「麻婆アスパラガス」レシピ担当沼田香余『薬膳生活レシピ開発BOOK Vol.3 冬 季節薬膳』