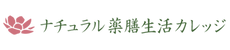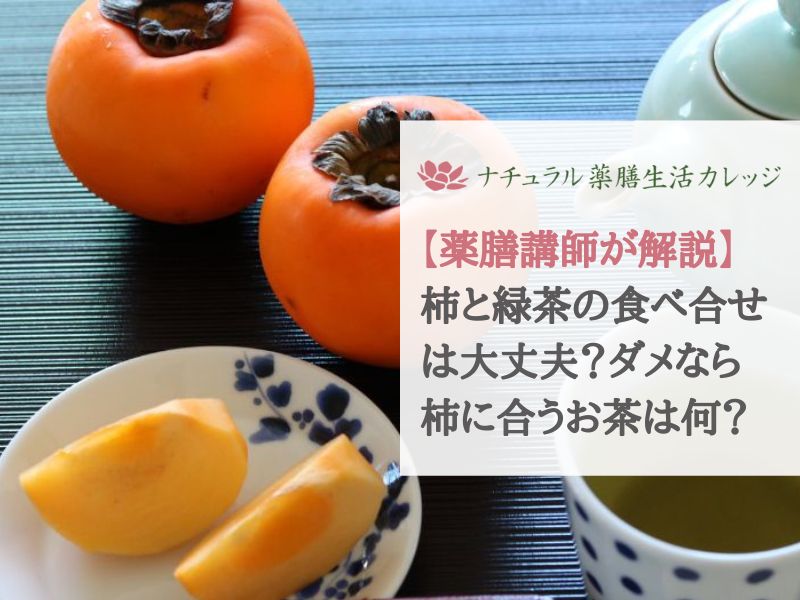こんにちは。薬膳講師歴15年の須崎桂子です。

柿と緑茶の食べ合わせで起こりやすい便秘の問題。
薬膳を生んだ中医学の視点からレッスンでお話しました。
すると、「柿と合わせるなら、何のお茶がよいのですか?」と、生徒さまから質問が・・・
確かに柿でお茶うけタイム、緑茶がダメなら何を飲んだらいいのか。
緑茶をよく飲む日本人なら、あたりまえの疑問です。
・柿と緑茶の組み合わせが、便秘になりやすい理由。
・柿を食べて一緒に飲んでも便秘になりにくい、薬膳茶やメディカルハーブの考え方。
便秘症だけれど柿を食べたい皆さんにも、どう答えたか分かち合います。

目次
柿を食べながら緑茶を飲むと便秘になる理由
柿を食べながら緑茶を飲むと便秘になりやすいのは、どちらも渋味のあるタンニンを多く含むから。
薬膳を生んだ伝統医学の中医学と、現代医学の要素を含むメディカルハーブの視点から解説します。
中医学では便秘に「禁忌・注意」の組み合わせ
中医学で柿と緑茶が組み合わせ注意なのは、相反(そうはん)という注意喚起に該当するからです。
柿と緑茶の相反で起こり得るのは「便秘」。
相反はあるふたつの生薬を一緒に使うと、何らかの健康被害が起こるかもしれないという警告。
中医学に基づく薬膳では、生薬と重複する食材の薬膳素材同士に当てはまる場合があります。
だから、漢方薬の配合と同じように薬膳を組み立てるときも、相反に気をつけるのです。
「相反で健康被害」と聞くと、心配になりますね。
しかし薬膳素材は大部分が一般食品で、作用は穏やか。命に関わる相反の症状は、ほとんどありません。
柿は普通の果物ですが、止咳平喘類(しがいへいぜんるい)の薬膳素材。喉を潤して咳を止める働きがあります。でも、便秘症には薬膳で禁忌・注意。
緑茶は、清熱類(せいねつるい)の薬膳素材で生薬でもあります。解熱のほか、下痢を止める止瀉(ししゃ)にも作用。日本薬局方にも、チャ(茶)という生薬として収載され、日本漢方に配合されています。
柿も緑茶も薬膳素材の作用に関して「止」の文字が含まれていますね。
「止」は、臓腑器官に直接働きかけて、ぎゅっと機能を抑制することを指します。
中医学では肺と大腸はつながりが深いとされていますが、柿も緑茶も呼吸器に作用する薬膳素材。
渋味が肺に作用して咳き込むのを抑える働きは、大腸にも連動してお通じを促す蠕動(ぜんどう)運動も抑えると考えます。
柿と緑茶が相反である論拠は、伝統医学の長い歴史を通じた経験則。
中医学の先人たちは数百年前から、渋味の摂り過ぎは便秘になりやすいと臨床経験で分かっていたのです。

「タンニン」で大腸を締めるメディカルハーブ
植物の薬理作用を健康管理に使うメディカルハーブの分野で、緑茶は収斂(しゅうれん)に働くタンニンハーブとして知られています。
ここで言う薬理作用は、植物化学成分が生体の健康管理に役立つ何らかの働きのこと。
メディカルハーブは、東洋と西洋の伝統医学で使われてきた様々な薬草たち。生薬のほか、食品の野菜・果物・ハーブと重複する植物が含まれています。
現代になって、こうした植物の薬理作用の成分が、科学的実験で検証・実証されるようになりました。
収斂は、中医学の「止」とほぼ同義。臓腑器官をぎゅっと引き締めて機能を抑制する働きです。
タンニンが収斂するのは、タンパク質を固める性質があるからです。
タンニンは渋味を持つ植物化学成分。細胞を老化から守る抗酸化作用で有名な、ポリフェノールの一種。
一方、柿に含まれるタンニンも、品種別の含有量や、植物細胞の中にどんな形で存在するのか、などの実験が行われています。
渋い渋柿にタンニンが入っているのは当たり前。では渋抜きされた甘柿はどうでしょう?
実は甘柿にも、舌で渋味を感じにくい形で水に溶けないタンニンが残っています。
柿を食べるときに緑茶でお茶うけしたら、一度に多くのタンニンが体に入ることになりますね。
だから特に、タンニンの刺激で大腸がぎゅっと収斂しやすい人は、柿と緑茶で便秘になるリスクが高いのです。

薬膳茶の視点で考える「柿に合うお茶」
便秘予防に、「柿を食べるときは緑茶は飲まないようにしよう」。
それで納得ならよいのですが・・・、何か代わりに飲みたい人もいますよね。
「では柿を食べるときは、どんなお茶ならいいのですか?」
生徒さまから聞かれたこともあり、「柿に合うお茶」を薬膳茶の視点で考えてみました。
「薬膳茶」とは
薬膳は、健康管理の目的に合わせ、中医学理論で組み立てる食事療法。
だから薬膳茶も目的によって、
・何の茶剤を
・単体か複数のブレンドか
・どんな淹れ方か
など等、
決めてから中医学理論で処方する飲むセラピーです。
狭義のお茶
但し薬膳茶の「茶」、という言葉はクセモノ。
茶の意味を狭義で限定的に捉えて、タンニンを含む「チャの木」の茶葉を加工した緑茶や紅茶や烏龍茶などが「お茶」だと考える人がいるからです。
例えば以前、お茶を狭義で捉えている生徒さまに、小豆を煎じて淹れた薬膳茶を紹介しました。
すると、「小豆でもお茶になるのですか?」と驚かれたことがありました。
豆類が薬膳茶の材料なるとは、それまで考えてもみなかったのだそうです。
広義のお茶
当スクールでは一般的な飲み物はすべて「お茶」と呼ぶ、広義の意味で薬膳茶と表現します。
ブレイクタイムや食後に愉しむ飲み物は、ほとんどが薬膳茶にアレンジOK。
コーヒー、紅茶、ハーブ、ジュース、ソーダ、スムージー、生薬の煎じ液・・・、健康管理の目的に合う飲み物として組み立てれば、すべて薬膳茶になると考えるからです。
柿に合う「お茶」を質問した生徒さまにも、狭義または広義のお茶を提案して欲しいのか、まず確認。
広義のお茶で、緑茶の代わりに柿に合う飲み物を知りたいとのことでした。

柿に合う薬膳茶の具体例
タンニンゼロで温かくして飲む「麦茶」
柿と一緒に飲むなら絶対にタンニンを含まないお茶がよい人には、スーパーで買える身近な麦茶がお勧め。
タンニンはもちろんカフェインもゼロ。だから飲んだとき、口腔内の粘膜を刺激する渋味を感じません。
麦茶の材料は大麦やはだか麦。
香ばしく焙煎したものを、水から煮出したり、水出ししたりして、麦茶として飲みます。
大麦もはだか麦も薬膳素材で、中医学ではどちらも体を冷やす分類です。
柿も体を冷やすので、麦茶と愉しむ場合は温かく淹れて飲むのがお勧めです。

タンニンゼロで緑茶のように飲める「桑茶」
もっと緑茶のような感覚で、柿と一緒に楽しめるタンニンゼロのお茶がよい人には、桑茶という選択肢もあります。
桑茶の材料は、蚕が食べる桑の葉。メディカルハーブでもあり、マルベリーと呼ばれています。
麦茶と同じように、タンニンゼロで、ノンカフェイン。
下の参考画像は、煎茶のように葉を細かく加工した茶剤を、ポットに入れて熱湯で蒸らし茶葉を漉して淹れた桑茶です。
見た目はまるで日本茶のようですが渋味がなく、単体でとても飲みやすい薬膳茶になります。
このほかにも、抹茶のようにパウダー状に加工した桑茶も市販されています。
パウダータイプはお湯に溶いて飲むので、桑の葉に含まれる食物繊維やミネラルなどを「一物全体(いちぶつぜんたい)」すべて摂れるメリットがあります。
桑の葉も麦茶のように体を冷やす働きがあるので、柿といただくなら温かく淹れて飲むのがよいでしょう。

タンニン少なめの緑茶「玄米茶」
「柿とお茶を愉しむなら、やっぱり日本茶。」という方には玄米茶という朗報があります。
「温かい薬膳茶を淹れて、柿と一緒に愉しむ」目的を決めたとしましょう。
でも便秘症で日本茶が好きなのに、柿と緑茶で便秘になりやすいのを知ってしまった。。。
その場合は中医学理論で、便秘予防に選べるチャの茶剤が無いか調べて絞り込みます。
・タンニンの少ないチャの茶剤
チャの木の茶葉が原料の緑茶には、タンニンが多いので避けるのが基本。
しかし、チャの茶剤は育て方や加工方法により、次のようにタンニンの含有量がずいぶん違います!
100mlあたり チャ由来の茶剤 タンニン含有量
・玉露 230mg
・煎茶 70mg
・ほうじ茶 30mg
・玄米茶 10mg
・烏龍茶 100mg
・紅茶 100mg
玄米茶は緑茶の種類の中でも、タンニンが煎茶の7分の1と少なめ。
紅茶や烏龍茶と比べると、タンニンは何と10分の1。
玄米がミックスされているので、チャの使用量が少ないからです。
秋に柿を緑茶と味わいたいなら、タンニンゼロではありませんが、玄米茶が選択肢に残されています。
茶剤に対する生体反応は個人差がありますので、実際に試してみるとよいでしょう。
ほかにもタンニン少なめのほうじ茶で、柿との組み合わせもどうだろうか、など。
自分のテイストに合っていて、便秘にならなければ、これから柿とのお茶うけに愉しめますね。

タンニン少なめの豆類「黒豆茶」
実は生徒さまから、「柿と一緒に黒豆茶ならどうですか?」というご質問も頂いていました。
緑茶の代わりに、柿と豆類のお茶を組み合わせるのは、よい発想ですよね。
豆類のお茶では、便秘になるリスクは低いです。
でも考えてみたら、黒豆の植物色素成分の黒い色のアントシアニンも、渋味のあるポリフェノールの仲間。
タンニンもポリフェノールの一種ですが、多くの植物には多かれ少なかれ色々なポリフェノールが含まれています。
黒豆は大豆の仲間でイソフラボンも含む薬膳素材ですが、これもポリフェノールの一種。
イソフラボンには、女性ホルモンのような薬理作用があるので、ダイズは更年期の女性に使われるメディカルハーブでもあります。
黒豆茶のタンニン含有量のデータが手元にないので、柿と黒豆茶で便秘にならないと断言はできません。
でも黒豆茶を飲んでも濃く淹れた緑茶ほど、タンパク質を固めるカテキンの影響で、口腔内の粘膜に強い刺激を感じることは稀。
黒豆茶はよっぽど濃く淹れなければタンニンは少ないので、緑茶のような苦味や渋味はほとんどありません。
黒豆茶や小豆茶のような豆類のお茶は、柿と一緒に飲んでも便秘を起こすリスクはそれほど高くないでしょう。

タンニン少なめのメディカルハーブ「ジャーマンカモミール」
柿と楽しむ茶剤には、タンニンが少ないメディカルハーブで薬膳茶を淹れるのもよいですね。
食後やリラックスタイムに柿と合わせるなら、ジャーマンカモミールなどがお勧め。
消化を助け、胃壁を守り、胃潰瘍の予防に使われ、よい香りでリラックスさせてくれる働きがあるからです。
植物にはポリフェノールのタンニンが、少量とはいえ含まれていることが多いです。
タンニンには太陽の強い紫外線で細胞が損傷しないように守る、抗酸化作用などがあるからです。
だからハーブティーでタンニンゼロを断言するのは難しいのですが、少なめのメディカルハーブを紹介します。

青りんごのような香りが独特なので、好みが分かれるところですが、意外に温かい牛乳と合わせると美味しいものです。
柿と一緒にミルク仕立てのハーブティーを飲むと、牛乳のタンパク質がタンニンによる口腔内の刺激を和らげる効果も期待できます。

まとめ
タンニンの多い柿と緑茶を組み合わせると、便秘になりやすいという先人の知恵とその理由を解説。
普通の緑茶ではなく、「柿に合うお茶」にはどんなものがあるか、薬膳茶の視点から紹介しました。
例に挙げたのは、タンニンゼロの麦茶と桑茶。タンニン少なめの、玄米茶、黒豆茶、ジャーマンカモミール。
植物に含まれる成分が生体に与える薬理作用の影響は、それぞれ個人差があります。
柿や緑茶で便秘が気になる人は、タンニンゼロや少なめの茶剤をを参考に、ご自身の体質に合う薬膳茶を組み立ててくださいね。
中医学理論で組み立てる薬膳生活を実践して、柿を味わいながら素敵なティータイムをお愉しみいただければ幸いです。
参考文献:
須崎桂子著『ナチュラル薬膳生活入門編』2013年
文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」
林真一郎著『メディカルハーブの事典』東京堂出版、2009年
伊達英代, 中島安基江, 竹田義弘, 新井清, 高尾信一.『広島県安芸太田町産柿「祇園坊」の可溶性タンニン含有による品質評価』広島県立総合技術研究所保健環境センター研究報告 No.22 p.21-23 2014 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/167067.pdf
福岡県薬剤師会『50.茶やコーヒーなどの嗜好飲料中のタンニン、カフェインの含有量』 https://www.fpa.or.jp/library/kusuriQA/50.pdf